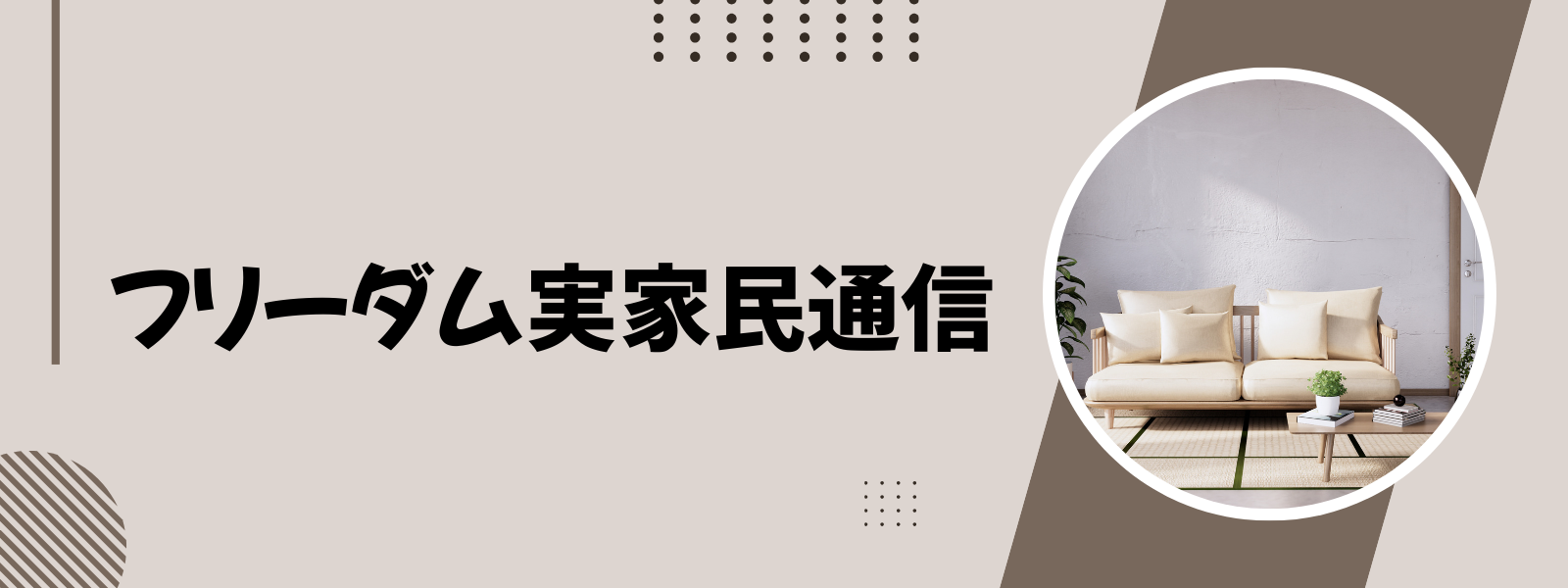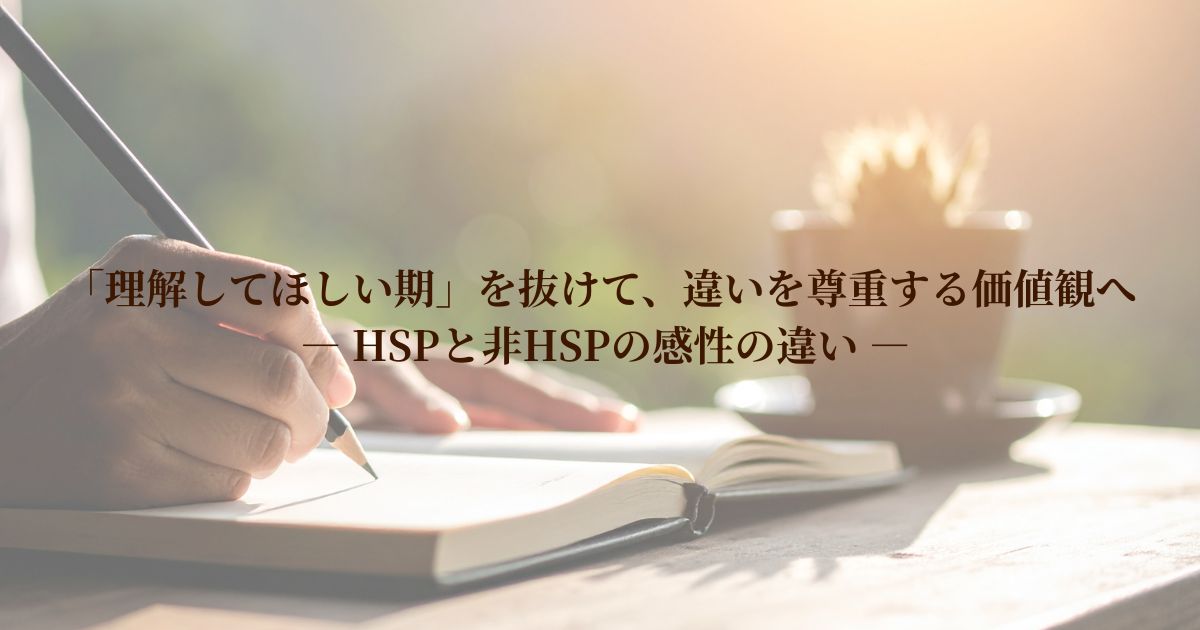自分が感じたことを素直に相手に伝えると
「考えすぎ」
「気にしすぎ」
そんな言葉を言われるたびに、気分が沈みました。
”繊細に感じとる”自分を見せまいと
「気にしない自分」を演じてきました。
でも、HSPという特性を知り、自己理解が深まるに連れ
演じ合わせてきた感性を、相手に理解して欲しい。
と、外の世界に理解を求めてしまう傾向が
「HSP=わがままな人」という意見になっているのかもしれません。
この記事では、私の失敗談を通して見えてきた
「理解してほしい」と思ったときの自分との向き合い方をお伝えします。
「理解してほしい」と思うのは自然なこと
結論から言うと、大事なのは
「理解される」より「自分を理解する」こと
HSPとしての特性を知ったとき
多くの人が最初に通るのが「理解してほしい期」です。
長いあいだ“自分の感受性を否定して生きてきた”からこそ
ようやく自己表現できる言葉が見つかり
「これが私なんだ」
と、わかった瞬間
それを外の世界にも理解してほしいと思うのです。
しかし、それは自然なこと。
“自己表現の回復期”に現れる、とても人間らしい反応です。
相手に理解を求めすぎてしまうのは「過去の痛みの反動」
「そんなに考えて疲れない?」
「重いよ。もっと軽く考えなよ。」
そんな言葉を繰り返し受けてきたことで、
心の中に「なんで、わかってくれないの?」という強い防衛反応ができていきます。
でも実は「理解されない=拒絶された」わけではないのです。
相手が理解できないのは、理解力の欠如ではなく
“感じ方の仕組みが違う”だけ。
HSPと非HSPの人では、見えている世界がまったく違うのです。
「伝わらない部分があっていい」と思えるようになるまで
お互いを完全に理解することは、誰にもできません。
だからこそ「違いを尊重する距離」を保つことが大切です。
「自分だって、100%相手を理解することはできない」
そう気づいたとき
私は少し傲慢だったのかもしれない、と思いました。
結果として今の私に、頻繁に連絡をくれる相手は
クーポンを知らせる広告です。
けれど、それでも残ってくれた相手と
お互いを尊重する、穏やかな関係を
再構築していきたいと、私は思っています。
HSPの最大の安心は、
他人の共感ではなく“自分の共感を自分に向けること”
相手に向けていた意識を、少しずつ自分に戻す。
これが、心の自然な再調整でした。
自分を理解することが、他人との優しい距離を生む
「理解されたい」という気持ちは
人として、当たり前な感情です。
むしろ、それだけ人と深くつながりたいと願っている証拠です。
しかし「私はこう感じるんだ」という感性に目を向け、
他者からの理解ではなく、感性の多様性を認めることで
相手との心地いい距離感が見つかっていきます。
伝わらないことがあっても大丈夫。
相手の感じ方も、自分の感じ方もそのままでいい。